(第8号 平成16年11月18日)
〜晩秋 里山の秋を体感して汗を流す〜
畑地の土づくりと進入路の補修作業を行う
柿の実も色づき、ハゼノキの紅葉の中で第7回活動(プレ活動)が11月13日(土)15名の参加で行われました。
午前中は赤米の脱穀作業を行う予定でしたが、前日早朝の激しい雨のために乾燥中の赤米穂が濡れ、水分を含んでいるために脱穀作業の農体験が出来ず、後日適切な日に地元の方の手を借りて、脱穀を行うことになりました。そのため、以前から不便さを我慢していた天理加茂木津線からの進入路の小川に接する一部が崩れている所や何回かの雨のために側路部が溝となって掘り取られている所、粘土質で軟らかく車輪が食い込む所等の通行が慎重にならざるを得なかった箇所の補修工事を行うことにしました。又、畑地作業は夏野菜の収穫時期が過ぎたことから、全ての野菜を撤去して、畑土を小型の耕運機で耕転を行いました。
昼食時は、少し肌寒さを感じましたが、ビールが喉を通る美味みは何時もの通りでした。温かいダイコン、コンニャク、ちくわの柚子味噌付けを副食にして、昼食が進み、関東煮とおでんの違いについて、 喧喧諤諤の談笑時間でした。デザートは地元産の柿の差し入れがありました。
午前中は赤米の脱穀作業を行う予定でしたが、前日早朝の激しい雨のために乾燥中の赤米穂が濡れ、水分を含んでいるために脱穀作業の農体験が出来ず、後日適切な日に地元の方の手を借りて、脱穀を行うことになりました。そのため、以前から不便さを我慢していた天理加茂木津線からの進入路の小川に接する一部が崩れている所や何回かの雨のために側路部が溝となって掘り取られている所、粘土質で軟らかく車輪が食い込む所等の通行が慎重にならざるを得なかった箇所の補修工事を行うことにしました。又、畑地作業は夏野菜の収穫時期が過ぎたことから、全ての野菜を撤去して、畑土を小型の耕運機で耕転を行いました。
昼食時は、少し肌寒さを感じましたが、ビールが喉を通る美味みは何時もの通りでした。温かいダイコン、コンニャク、ちくわの柚子味噌付けを副食にして、昼食が進み、関東煮とおでんの違いについて、 喧喧諤諤の談笑時間でした。デザートは地元産の柿の差し入れがありました。
| 午後の作業は午前の続きです。何分にも、機械類がないために全てが人力作業です。しかし、そこは「街づくり」の 経験が豊富な集団です。土木工事は慣れたものです。全員が自主的に行動して補修箇所の作業を行いました。路の縦断と軟らかくなった2ヶ所に有孔管を敷設し、
小川から砂や小石を採取して敷き詰めて小川に排水出来る様にしました。 崩れた箇所も杭を打ち込み、土嚢を詰めて補修を行いました。畑地の作業も大変です。雨で水分を充分に含んでいるため、耕転するのに一苦労でした。 |
|
|
進入路の排水補修作業風景 |
刈り取った茎や葉、草類は堆肥化するために一箇所に堆積しました。物置小屋の中も整理を行いました。今回の収穫は赤かぶが少々でした。参加していただいた皆様ご苦労様でした。
第8回活動は12月11日(土)です
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は畑の耕作、竹林の伐採等の予定です。道具が用意できれば餅つきを考えています。寒い時期になります。無理をせず、健康に気をつけて参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課
電話 0774−73−1518
11月13日活動記録写真
 |
 |
排水管の敷設作業をする |
小川から砂や小石を採取する |
 |
 |
砂や小石を敷き均す |
進入路の排水補修作業完了 |
 |
 |
畑地の耕転作業をする |
参加者の記念写真 |
一口鹿背山季節メモ
柿や柚子は今が収穫期です。「桃栗3年、柿8年、梅は酸い酸い13年、柚子の大馬鹿18年、林檎ニコニコ25年」といわれています。これは種から育てた木が実をつけるまでの年数だとされています。現在流通している苗木は接木ですのでこんなに年数は必要としません。
第7回活動(プレ活動)の参加者(15名)
富永区長、井上、広瀬、大森、長尾、鈴木、高須、加藤、中川、谷、藤原、佐竹、鹿野、赤井、大坪 でした。
|
|
(第7号 平成16年10月21日)
〜台風一過 秋晴れのもと稲刈りをする〜
赤米の刈り取りと竹炭材料の切り出しを行う
台風の影響で1日延期して、第6回活動(プレ活動 )が10月10日(日)13名の参加で行われました。
午前中の作業は稲架(はざ)作りと赤米の刈り取り、稲架掛けです。富永区長、富永(ふるさと農園)さんの指導で行いました。稲架作りは周辺に育っている淡竹を切り出して、組み立てを行いました。竹の3本、4本の組結びは紐が滑らないようにするためのコツがあり、農作業での一つの知恵を教わりました。
さて、いよいよ刈り取りです。順調に育った赤米も1.3 m程になり稲穂も充分に実り、茎も太く丈夫です。しかし、台風による風や幾多の雨の影響で、稲が総倒れの状態です。その上に長く水に浸かっていたために水を充分に含み、刈り取るのも稲架に掛けるのも一苦労しました。
刈り方や稲の束ね方、掛け方も初めてでも「鹿背山素人農民」の力は凄い。各人が分担を弁え、約1時間で作業は終わりました。
|
昼食は、前日から用意した材料で豚汁を作りました。 また、作業小屋の近くにある山栗を拾い集めて、茹でて食味しましたが小粒でも意外と甘味があり、秋を賞味しました。台風一過で気温も湿度も高く、汗を充分に掻いた後の缶ビールの美味さは、何時もの通り格別でした。 午後の作業は竹炭材料の切り出しと畑や畦道周辺の草刈り、秋野菜の植付けを行いました。 |
竹炭用の竹は孟宗竹です。地際の太い部分の切り出しは危険が伴います。数人での作業です。釜に入る様に切り揃え適当な大きさに 割り束ねて自然乾燥のために休憩場に搬入しました。畑や畦の草もよく伸びます。足元の確保を怠ることは出来ません。
ニンニク、ラッキョウ、玉ねぎ等の植え付けを行いました。今回は晴れに恵まれましたが、汗を掻き続けた一日でした。拾い集めた山栗を土産に家路につきました。皆様、ご苦労様でした。
第7回活動は11月13日(土)です
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は脱穀、畑の耕作と除草、竹林の伐採、野菜の収穫等の予定です。
寒さを感じる時期になります。無理をせず、健康に気をつけて参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課
電話 0774−73−1518
10月10日活動記録写真
 |
 |
淡竹材で稲架づくりをする |
稲架が出来上がり稲を掛ける |
 |
 |
稲の刈取りと稲架掛けをする |
昼食風景(「農」談義中です) |
 |
 |
孟宗竹で竹炭材を作る |
参加者の記念写真(加藤氏撮影) |
一口鹿背山季節メモ
赤米の特徴
稲の原産地は中国の「雲南省」といわれる。果皮、種皮の部分に赤色系色素(タンイン系)を含むために、 玄米は赤褐色になる。糠全て取り除くと白米になる。
第6回活動(プレ活動)の参加者(13名)
富永区長、富永(ふるさと農園)井上、堀内、長尾、鈴木、加藤、中川、北村、鹿野、赤井、谷、大坪でした。
(第6号 平成16年9月14日)
〜残暑の秋空の元で敷地整備作業をする〜
畑地整理と収穫作業、秋植え播種を行う
山から降りて来たアキアカネが飛び交う中で、第5回活動(プレ活動)が9月11日(土)14名の参加で行われました。
午前中の作業は、畑の作物の整理です。春植えした作物の多くは自然の恵みを与えてくれました。収穫時期が過ぎていますが、元気に小さな実を付け、花を咲かしている作物もあります。大地からの贈り物に感謝する心が大切です。誘引をして結束し直すことで、新しい実りの恵みを楽しむことが出来ます。
サツマイモの収穫も行いました。「里山体験」での農の楽しみの一つです。収穫は少し早いために、小ぶりの実りとなりましたが、予想外に多く収穫することができました。丸みのもの、細長いもの、店先に並べても恥ずかしくないもの等、形も様々です。これが自然の農作物です。
来年に向けての水田用地の草刈機による除草も前回に引き続き行いました。雑草がよく茂り足元の確認が大変です。慣れた手付きですが、事故のない様に注意しての作業となりました。
9:50学研集合
作業内容は畑の耕作と除草、水田用地の草刈作業、竹林の伐採、林地探索の予定です。
秋の涼しさを感じる時期になりますが無理をせず、健康に気をつけて参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
午前中の作業は、畑の作物の整理です。春植えした作物の多くは自然の恵みを与えてくれました。収穫時期が過ぎていますが、元気に小さな実を付け、花を咲かしている作物もあります。大地からの贈り物に感謝する心が大切です。誘引をして結束し直すことで、新しい実りの恵みを楽しむことが出来ます。
サツマイモの収穫も行いました。「里山体験」での農の楽しみの一つです。収穫は少し早いために、小ぶりの実りとなりましたが、予想外に多く収穫することができました。丸みのもの、細長いもの、店先に並べても恥ずかしくないもの等、形も様々です。これが自然の農作物です。
来年に向けての水田用地の草刈機による除草も前回に引き続き行いました。雑草がよく茂り足元の確認が大変です。慣れた手付きですが、事故のない様に注意しての作業となりました。
| 昼食は、畑直送のナスをアルミ箔に包んでの焼きナス料理、ゴウヤを豆腐と卵で炒めた沖縄料理、サンドマメの油炒め、「自称名人」が焼いた焼き芋、ラーメンとおにぎりなど。冷えたビールを片手に残暑の秋空のもとで談笑して作業の疲れを癒しました。 午後の作業は引き続き水田用地の除草、農道沿いの竹林等の伐採を行いました。農道に覆い被ぶさる様に茂っていた急斜面の雑木や竹を取り除きました。足元が安定せず難しい作業でした。 |
|
|
秋植え作物の播種作業 |
畑には生石灰を散布して、耕転し畝づくりをしてから秋植えの播種を行いました。
収穫はサツマイモ、ゴウヤ、ナス、サンドマメ、ピーマンでした。秋とはいえ暑い一日でした。参加していただいた皆様お疲れ様でした(東京に転勤された杉崎様に参加していただきました)。
第6回活動は10月9日(土)です。
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は畑の耕作と除草、水田用地の草刈作業、竹林の伐採、林地探索の予定です。
秋の涼しさを感じる時期になりますが無理をせず、健康に気をつけて参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業計画第一課
電話 0774−73−1518
9月11日活動記録写真
 |
 |
楽しいサツマイモの収穫作業 |
細いもの、大きいもの種々 |
 |
 |
農道沿いの竹の伐採作業 |
赤米も順調に生育しています |
 |
 |
水田用地の草刈作業 |
ゴウヤと豆腐と卵で沖縄料理中です |
鹿背山一口メモ
鹿背山の里山にもオニヤンマ、アキアカネ、シオカラトンボ(雄)、ハグロトンボ、ノシメトンボ、イチモンジチョウ、コミスジ、ウラナミジャノメ等が訪れました。
第5回活動(プレ活動)の参加者(14名)
垣見、広瀬、堀内、長尾、前田、杉崎、後藤、山崎、北村、橋本、佐竹、鹿野、藤原、大坪でした。
(第5号 平成16年8月26日)
〜 残暑厳しい中で除草作業をする 〜
実りの秋も間近、汗を掻き自然と向きあう
アブラゼミの泣き声も一段と大きく、残暑厳しい中での第4回活動(プレ活動)が8月21日(土)に18名の参加で行われました。
午前中の作業は曇り空でしたが、厳しい暑さの中で生い茂る雑草との戦いとなりました。畑の野菜類は収穫時期を過ぎたものが多く、 少しの実りが雑草と競い合っていました。手作業での人海戦術です。時期を過ぎたものは抜き、収穫の見込みのあるものは丁寧に周囲 の雑草を抜いて行きます。汗にまみれての自然との付き合いです。小言も言わずに農の作業です。
農道も畦法面、作業スペースも雑草が力強く茂っています。こちらは草刈機3台での格闘となりました。操作も馴れたもので、雑草が次々に倒れて行きます。事故のないように注意しての作業でした。
サツマイモの試し掘りを子供に楽しんでもらいました。少し小さめで、細い実りでした。来月が楽しみです。
冷えたビールと冷ヤッコ、インスタントラーメンに持参のおにぎり等。一汗を掻いた後の緑の濃い、 農の雰囲気の中での談笑は素晴らしい「つまみ」です。試し掘りのサツマイモで即席焼き芋をしました。
| アルミホイールに包んで、焚き火の中に。約20分後、達人の一声で焼き上がりは満点。甘くて、美味しい焼き芋の出来上がり。 富永さんからの差し入れの「イチジク」は甘さや独特のプチプチ感、冷やし具合も調度よく、一足先に秋の味覚を味わうことが出来ました。 午後の作業は畑や農道等の除草作業に加えて、約1mに育った赤米の水田での草取り、 直播陸稲米の草取り、来年に向けての水田用地の草刈機による除草、枯れ草の焼却等の作業を行いました。 7月の活動日には収穫間近であったトウモロコシが「鳥の餌」になり、また、収穫時期を逸してしまい、実りを味わうことが出来ませんでした。 |
|
|
サツマイモも順調に育っています |
来年は香ばしい醤油の焦げる臭いを楽しむことが出来る様に反省しきりです。収穫はゴウヤ、シシトウ、ナスビ、サンドマメ、ミニトマト、ヒョウタン、ヒマワリ、サツマイモ等でした。今回は暑さに耐えながらの作業でした。参加の皆様ご苦労様でした。
第5回活動は9月11日(土)です。
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は秋植え作物の植付けと畑の耕転、サツマイモの収穫作業等を行う予定です。夏季の疲れが出て来ます。無理をせず、健康に気をつけて気軽に参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課
電話 0774−73−1518
8月21日活動記録写真
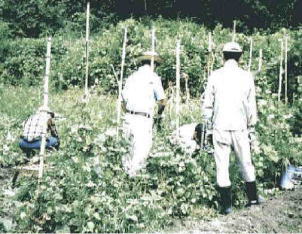 |
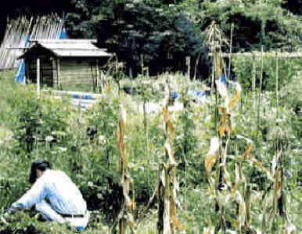 |
暑さに耐えて手作業による除草作業 |
トウモロコシは収穫時期を逸する。 |
 |
 |
元職員下村さんの子供によるイモ掘り |
来年に向けての水田用地の除草作業 |
 |
 |
畦道の草刈機による作業 |
参加者の記念写真 |
一口鹿背山季節メモ
夏も終わりに近づいて、昆虫達も忙しい時です。鹿背山の里山にもオニヤンマ、ギンヤンマ、ナツア
カネ、シオカラトンボ(雄と雌)、ハグロトンボ、モンシロチョウ、タマムシ等を見かけました。
第4回活動(プレ活動)の参加者(18名)
富永(ふるさと農園)、下村夫妻と子供2人、垣見、末永、堀内、井上、長尾、前田、加藤、高須、山崎、中川、橋本、鹿野、大坪でした。
|
|
(第4号 平成16年7月30日)
〜 空梅雨の猛暑のなかで農作業をする 〜
初収穫と除草作業で農体験を満喫する
早朝の一時的な激雨も上がった中で第3回活動(プレ活動)が7月10日(土)10名の参加で行れました。
午前中の作業は雨上がりの後、汗にまみれての雑草との戦いになりました。収穫が楽しみな農作物の生育も順調ですが、雑草も元気よく茂りを続けています。これが自然なのでしょう。水田を畑に転用しているため、生長がよく様々な植物が繁茂しています。鍬除草と釜の手作業により、それぞれが 孤軍奮闘しましたが効率はよくありませんでした。(当然です。無理をせず、マイペース活動が信条です)
幼虫による食害も懸念されましたが、炭焼きをした時に採集した竹酢を薄めての散布効果で、アブラムシやイモムシ等の発生もほとんどない状況での除草作業となりました。
>
作業内容は水田の除草、畑の手入れ、竹材による拠点施設の整備作業の予定です。
夏季の作業です。無理をせず、健康に気をつけて自由に活動することが信条です。
気軽に参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
7月1日より、「都市公団」は「都市機構」に衣替えしましたが、人事異動もあり、この鹿背山倶楽部の初期からのメンバーであった杉崎さんが東京へ転勤となりました。
(第3号 平成16年6月21日)
赤米の実りを楽しみに小雨のなかで汗を掻く
9:50学研集合
作業内容は水田の除草、畑の手入れ、水路整備と竹材による拠点施設の整備作業を行う予定です。夏季の作業です。無理をせず、健康に気をつけて自由に活動することが原則です。気軽に参加してください。
午前中の作業は雨上がりの後、汗にまみれての雑草との戦いになりました。収穫が楽しみな農作物の生育も順調ですが、雑草も元気よく茂りを続けています。これが自然なのでしょう。水田を畑に転用しているため、生長がよく様々な植物が繁茂しています。鍬除草と釜の手作業により、それぞれが 孤軍奮闘しましたが効率はよくありませんでした。(当然です。無理をせず、マイペース活動が信条です)
幼虫による食害も懸念されましたが、炭焼きをした時に採集した竹酢を薄めての散布効果で、アブラムシやイモムシ等の発生もほとんどない状況での除草作業となりました。
>
| 昼食時は少し小ぶりのエダマメを茹でた酒肴でビールを「グィー」と一飲み。小川で冷やしたビールで忘れられない味。
即席のナスビの浅塩揉漬けもここだけの味。
富永(ふるさと農園)さんからの差し入れの冷えたトマトも忘れられない味でした。 午後は水田の施肥と除草、日照確保のため雑木の伐採作業を行いました。富永さんの指導で有機肥料(窒素、リン酸、カリ含む)の散布を行い約40cmに育った 稲苗を倒さないように慎重に水草取りを行いました。 稲作には陽当りが大切です。水田の南側の雑木林が日陰を造るために一部伐採作業を行いました。 |
|
|
順調に育ち、収穫間近かのトウモロコシ |
初収穫はゴウヤ、枝豆、シシトウ、ナスビ、サンドマメ、ミニトマトでした。湿度が高く、汗を掻き続けた作業の一日となりました。参加していただいた皆様お疲れ様でした。
第4回活動は8月14日(土)を21日(土)に変更です
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は水田の除草、畑の手入れ、竹材による拠点施設の整備作業の予定です。
夏季の作業です。無理をせず、健康に気をつけて自由に活動することが信条です。
気軽に参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市機構関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第一課
電話 0774−73−1518
お知らせメモ
7月1日より、「都市公団」は「都市機構」に衣替えしましたが、人事異動もあり、この鹿背山倶楽部の初期からのメンバーであった杉崎さんが東京へ転勤となりました。
7月10日活動記録写真
 |
 |
暑さに耐えて手作業による除草作業 |
稲には日照が命。雑木林の伐採作業 |
 |
 |
稲が丈夫に育つように追肥をする |
水田の稲間に茂る水草類 |
 |
 |
記念すべき初収穫の野菜です |
参加者の記念写真 |
第3回活動(プレ活動)の参加者(10名)
富永(ふるさと農園)、中村、垣見、堀内、広瀬、長尾、加藤、中川、山崎、大坪でした。
|
|
(第3号 平成16年6月21日)
〜ロマンへの誘い 古代米の田植えをする〜
赤米の実りを楽しみに小雨のなかで汗を掻く
燕が飛び交う小雨の中で第2回活動(プレ活動)が6月12日(土)19名の参加で行われました。
午前中は赤米の田植えを行いました。何分にも今は機械の時代、昔からの手植えのやり方は経験も見聞する機会も少ないため、手解きを受けての作業となりました。地元にお住まいの冨永区長と冨永翁の指導で田植えを行いましたが、泥に手足をとられて転ぶ者、足が抜けなくなり助けを求める者、植付けが上手く出来ずにやり直すなど悪戦苦闘しました。
小雨のなかで、また、長年放置されていたために、素足で田に入るのは危険であるため、履物を履いて作業したことも原因かもしれません。しかし、馴れた手つきで感心させた“隠れ農民”の方もおられました。手植えの難しさ、楽しさを通じて自然と向き合う生活を学ぶ貴重な体験をしました。
午前中は赤米の田植えを行いました。何分にも今は機械の時代、昔からの手植えのやり方は経験も見聞する機会も少ないため、手解きを受けての作業となりました。地元にお住まいの冨永区長と冨永翁の指導で田植えを行いましたが、泥に手足をとられて転ぶ者、足が抜けなくなり助けを求める者、植付けが上手く出来ずにやり直すなど悪戦苦闘しました。
小雨のなかで、また、長年放置されていたために、素足で田に入るのは危険であるため、履物を履いて作業したことも原因かもしれません。しかし、馴れた手つきで感心させた“隠れ農民”の方もおられました。手植えの難しさ、楽しさを通じて自然と向き合う生活を学ぶ貴重な体験をしました。
| 昼食時には、木津南の公団住宅にお住まいで、地元の農産品の品評会でも実績をあげておられる橋本夫妻の奥様が手作りされた黒米入りのおにぎり風小袋づつみの差し入れを全員で賞味しました。小さな竹細工籠入りで黒米の他にエンドウ豆が入っていました(皆、可愛さに心が和む)。 午後の作業は畑の枝豆、スィートコーン、ゴーヤ、サツマイモ、トマト等の畑の除草や直播水田の除草、 竹と丸太で階段の整備、水路沿いの進入路の補修工事等を行いました。 畑の野菜は順調に育っています。収穫が楽しみです。 |
|
|
昔ながらの小雨の中での田植え |
今回は小雨。昔ながらの小雨の中での田植えが降り続き、最後まで雨に濡れ、泥にまみれての作業日でした。皆様ご苦労様でした。
第3回活動は7月10日(土)です。(雨天中止)
9:50学研集合
乗り合いにて現地に行きます。現地集合は10:00です。
作業内容は水田の除草、畑の手入れ、水路整備と竹材による拠点施設の整備作業を行う予定です。夏季の作業です。無理をせず、健康に気をつけて自由に活動することが原則です。気軽に参加してください。
連絡先(鹿背山倶楽部事務局)
都市公団関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第二課
電話 0774−73−1521・1509
6月12日活動記録写真
 |
 |
赤米の苗が到着 |
手植えのやり方を教わる |
 |
 |
ラインに沿って植えていく |
田植え完了(上手く育つかな〜) |
 |
 |
畑の草取り作業 |
参加者の記念写真 |
里山メモ
古代米には赤米・黒米・緑米があり、野生稲の大部分は赤米であることから、赤米は米のルーツとされています。赤米はジャポニカ種でうるち米が多く、赤飯の起源とされる。黒米はインディカ種でもち米が多く、おはぎの起源とされる。緑米はもち米で粘りが強く甘みがあり、生産者が少なく幻の米といわれています。
|
|
(第2号 平成16年5月20日)
〜 木津北里山再生の活動はじまる 〜
晴天のもと23名の参加でスタート
新しい里山文化の創造を目ざして、鹿背山地区で自然との触れ合いや農業体験を通じて楽しく汗を掻き、新しいコミュニチィづくりを模索する「鹿背山倶楽部」の第1回活動(プレ活動)が5月8日(土)に木津町職員、公団職員、公団関連職員、公団OB、OB家族の参加を得て行われました。
| 当日は晴天に恵まれ、ウグイスの囀るなか、学研本部中川課長から趣旨と今後の活動内容の説明を聞いた後、参加者の自己紹介が行なわれました。 午前中は木津北地区内の現地状況の視察を行いました。長年放置されていたために竹林が優先し木漏れ陽もなく、 薄暗くなったところや倒竹も多くありました。 使用されていなかったために荒廃した水田や畑の状況や竹林の試験伐採地、地区の中央部にある八王子恵比寿神社等を踏査しました。 楽しみの昼食は地産地消の精神で竹茶碗や箸を手作り、持参のおにぎり等と事務局で用 意したたっぷりの素麺に舌づつみをうち、適度に個々が満足するアルコール量で一時の休憩を談笑して過しました。 午後の作業は枝豆、スィートコーン、ゴウヤ、サツマイモ、トマト等の 畑の除草や直播水田の除草、竹と丸太で階段の整備、水路沿いの進入路の補修工事等を行いました。 |
|
|
昔ながらの小雨の中での田植え |
都市公団関西文化学術研究都市事業本部事業部事業計画第二課
電話 0774−73−1521・1509
※ 鹿背山倶楽部の会員を募集中です。
(正会員2,000円/人・年 賛助会員一口5,000円/年)
5月8日活動記録写真
 |
畑作業中の風景 |
 |
 |
現地見学 |
サツマイモ植付け後の施肥 |
 |
 |
野菜の手入れ |
参加者集合写真 |
※今後の活動日は原則として各月の第2・4土曜日とします。
|
|
(第1号 平成16年4月17日)
〜里山で緑に包まれて、いい汗をかきませんか〜
いよいよ木津北里山再生の活動組織を立ち上げることとしました。
木津中央地区においては営巣を確認されたオオタカについて、地区内での生息保全が極めて難しいことから、営巣している木津北地区も含めて対応が可能かどうかを議論されています。
このことから、地区に放置されてきた里山環境の改善を図ることができれば、有効な生息の「代償措置」となる可能性も指摘されており、新しい都市生活における自然との共生生活を模索するケースにもなります。自然環境の保全は開発の中止だけではありません。高齢化社会を迎えた今日は日本の原風景を形成する大きな要素の里山生活が放棄されて います。
樹林が鬱そうと茂り孟宗竹が森林の植生を変えてきています。大切な自然の生態系が崩れてきています。各地で自然環境を修復し、自然との触れ合いの中から「ゆとり」のある豊かな都市生活を求めて里山の活動に参画している人達が増えきています。私たちも心のリフレッシュと明日への活力のために、週末にいい汗を流してみませんか。
10:00 現地集合 活動内容の説明
10:30 下草刈りと畑地の耕転作業
12:00 昼食(冷た〜いビール+)
13:00 畑地の耕転作業と野菜の植え付け
15:00 野草の探索
16:00 作業終了(楽しくもう一度ビールを飲み干す)自由解散
このことから、地区に放置されてきた里山環境の改善を図ることができれば、有効な生息の「代償措置」となる可能性も指摘されており、新しい都市生活における自然との共生生活を模索するケースにもなります。自然環境の保全は開発の中止だけではありません。高齢化社会を迎えた今日は日本の原風景を形成する大きな要素の里山生活が放棄されて います。
樹林が鬱そうと茂り孟宗竹が森林の植生を変えてきています。大切な自然の生態系が崩れてきています。各地で自然環境を修復し、自然との触れ合いの中から「ゆとり」のある豊かな都市生活を求めて里山の活動に参画している人達が増えきています。私たちも心のリフレッシュと明日への活力のために、週末にいい汗を流してみませんか。
作業日 平成16年4月17日(土)10:00〜
場 所 木津北地区鹿背山にて(地図参照)
作業内容 下草狩りと畑地の耕転と野草探索など
活動のスケジュール
10:00 現地集合 活動内容の説明
10:30 下草刈りと畑地の耕転作業
12:00 昼食(冷た〜いビール+)
13:00 畑地の耕転作業と野菜の植え付け
15:00 野草の探索
16:00 作業終了(楽しくもう一度ビールを飲み干す)自由解散






